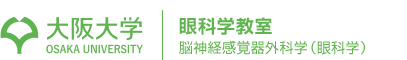目の構造とはたらき
■まず、目の構造とそのはたらきを知っておく必要があります。
■眼球の構造は、図に示しますように、前から角膜、水晶体網膜の順に構成されています。
■そのはたらきをカメラにたとえますと、角膜と水晶体がレンズの役割をして、網膜がフィルムに相当し、網膜に写った像が視神経から脳に伝わります。
■このどの部分が病気になっても、視力が低下してしまいます。
■屈折異常は、角膜と水晶体によるレンズの度数と眼球の長さのバランスがくずれて、網膜に映し出される像がぼやけて、視力が低下される状態です。
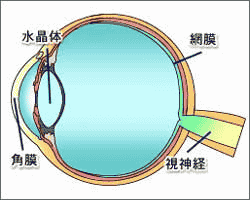
遠視とは?
■これに対して、遠視が強いと遠くも、近くも眼鏡やコンタクトレンズがないとぼやけて見えます。
■ただし、若くて水晶体が十分に調節できるときは、軽度の遠視であれば、遠くも近くも良く見えます。ただし、目が疲れやすくなります。
■その原因は、角膜と水晶体のレンズの度数に比べて、眼球の長さが短いことにあります。レンズの度数が足りないわけですから、凸レンズ(プラスレンズ)を加えてやると見えやすくなります。
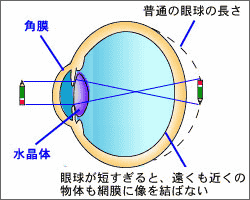
老視(老眼)とは?
■老眼は、老化によって水晶体の調節力が減少することで、大体40歳台より始まります。
■老眼になった後の見え方は、もともとの屈折異常の種類によって違ってきます。
■目の良い場合(正視)には、元々、眼鏡なしで遠くも近くも見えていたのが、
老眼になると遠くは良く見えるが、手元は、眼鏡がないとかすんで見えます。
■近視の場合に老眼になると、若い間は眼鏡やコンタクトをすれば、近くも遠くも見えていたのが、
近くは眼鏡をはずさないと見にくくなります。
■遠視の場合は、近くと遠くで2種類眼鏡が必要となります。
■屈折矯正手術は、近視、乱視、遠視を軽くする手術ですが、老視を治療することはできません。
そのため40歳台以降は、近くを見るときには、もともと目が良かった人と同じ様に読書用の眼鏡が必要になります。
近視とは?
■近視は、近くはメガネやコンタクトレンズなしで見えるが、遠くはぼやけて見える状態です。
■その原因は、角膜と水晶体によるレンズの度数に対して、眼球の長さ(眼軸長)が長すぎるため、遠くのものは網膜に像を結ばなくなる状態です。原因としては、レンズの度数が強すぎる場合と、眼球が長すぎる場合があります。
■レンズの度数が強すぎるため、凹レンズ(マイナスレンズ)を加えてやると見えるようになります。
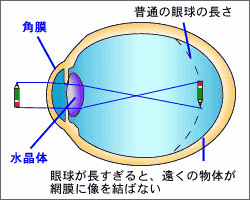
乱視とは?
■乱視は、近視や遠視と比べてわかりにくいものですが、
簡単に言えば、角膜や水晶体の形が歪んでいて、縦と横で近視や遠視の度数が違う状態です。
そのため、乱視が強いと縦と横で線の太さが違って見えたりします。
縦と横で度数が違うので、円柱レンズを足してやると、縦と横で度数が同じになります。
残った近視や遠視は、マイナスレンズやプラスレンズをその上から加えて矯正します。